![駒牽朱印[16個入]吹き戻し付](http://bizenya.co.jp/cdn/shop/products/020_6863dbb2-d0a7-4d0b-9fc3-6e98defefc28_300x.jpg?v=1612961278)
![駒牽朱印[21個入]吹き戻し付](http://bizenya.co.jp/cdn/shop/products/komabiki-21_300x.jpg?v=1612961278)










駒牽朱印 進物箱入
胡麻入りで風味良い薄焼き煎餅で、こし餡入りの大福饅頭を挟んだ、軟らかく歯切れ良いお菓子です。
バラ売りはございません。
10個入、16個入、21個入りには、「吹き戻し」が入っています。
24個入、32個入は、貼り箱に4個袋入が数量分入っています。「吹き戻し」は入っていません。
10枚入はレターパックプラスでお届け出来ます。
商品情報( アレルゲン 栄養成分 賞味期限 外寸)
| ○ 共通 | |
|---|---|
| アレルゲン(27品目中) | 小麦・卵・胡麻 |
| 賞味期限 | 25日~40日(直接当店発送より) |
| 栄養成分表示 | 駒牽朱印 4個袋入(1個あたり)/熱量101kcal, たん白質1.2g, 脂質 0.4g, 炭水化物 23.4g, 食塩相当量 0.01g (推定値) |
| ○ 24個入(4個入×6) | |
| 外寸(mm) | 270x280x65 |
| ○ 32個入(4個入×8) | |
| 外寸(mm) | 270x370x65 |
| ※表示は現在販売している商品の情報です。 お届けする商品と仕様、パッケージ等が変わることがございます。 | |
「駅馬・伝馬」の制度は奈良・平安から始まり、公用の役人が宿駅ごとに馬を乗り換えるのに利用しておりました。
徳川家康は関ヶ原の合戦後、従来の伝馬制を踏襲し東海道の宿駅ごとにこれを整備し伝馬役を置きました。
現在各地に残る「伝馬」の地名の多くは、この伝馬役を務めた町に由来しています。
徳川幕府は公用旅行者の朱印状に伝馬の宿を指定する際には「駒牽朱印」を公印として押しました。駒(馬)を牽(引)く人が描かれた趣あるデザインとなっております。
「駒牽朱印」の要は、北海道小豆のこし餡です。
≪手風琴のしらべ≫と同じ、北海道小豆から自社で製餡したあっさりしながら小豆の風味・旨みを閉じ込めた生餡をベースにしています。
餅に包んで丁度良い透明感のある甘みとなめらかさに炊き上げております。
富山県産餅米の牛皮粉から練り上げるお餅で薄くこし餡を包んであります。
パリパリの胡麻入り薄焼き煎餅でお餅を挟んで、つぶします。
やがて、煎餅は餅の水分を吸って、やわらかくなります。
餅菓子ですが、手に持っても手に付かず、端切れも良く食べやすいお菓子になります。
You may also like
よくあるご質問
-
個包装になっており、各々に脱酸素剤が入っていますので、個包装で賞味期限までお召し上がり頂けます。
-
4個入りが最小になります。
-
個包装には賞味期限は付いておりません。原材料などの一括表示もありません。
袋入り、箱入にはそれぞれ袋や箱に表示しています。
-
4個入であれば、袋の背面にシールで付いています。
箱入(10個・16個・21個)は、箱の蓋側面にシールで表示されています。
個包装個別には付いていませんので、袋や箱から取り出す際には、袋や箱に表示されている賞味期限をご確認下さい。
-
餅が固くなるので、冷蔵庫や冷所での保管はお勧めできません。
餅が固くなっても、風味は劣りますが、衛生上は問題無くお召し上がり頂けます。
-
「吹き戻し」は箱入(10個入・16個入・21個入)に1本ずつ入っています。
お問い合わせ下さい
なんでもお気軽にお問い合わせ下さい。
頂いたメールアドレスにお返事させて頂きます。また、携帯電話番号を頂いた場合、メールでご連絡が執れない場合にSMSでご連絡差し上げることもございます。
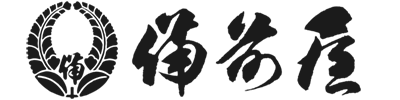
![駒牽朱印[16個入]吹き戻し付](http://bizenya.co.jp/cdn/shop/products/020_6863dbb2-d0a7-4d0b-9fc3-6e98defefc28_1200x.jpg?v=1612961278)
![駒牽朱印[21個入]吹き戻し付](http://bizenya.co.jp/cdn/shop/products/komabiki-21_1200x.jpg?v=1612961278)






















